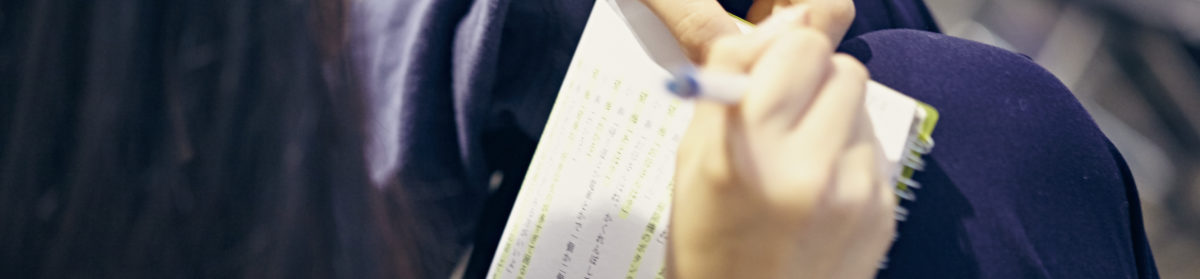2018年12月5日(水)、12日(水)、19日(水)の3日間、「伊藤俊也監督による俳優のための実践的ワークショップ」が行われます。開催にあたり、講師である伊藤俊也監督に緊急インタビューをしてきました。数々の名作を作られてきた伊藤俊也監督がどのように俳優と接してきたのかなど、興味深いお話を聞かせていただきました。聞き手は、アクターズ・ヴィジョン代表・松枝佳紀(まつがえ・よしのり)です。
——
マツガエ:伊藤俊也監督、まずはワークショップ講師を引き受けてくださりありがとうございます。大変貴重で光栄なことだと思っています。
伊藤俊也:いえいえ
マツガエ:アクターズ・ヴィジョンの監督によるワークショップは、俳優に演技を教えることを目的にしてはおりません。ともに映画を作りたいと思えるような俳優を見つけ出していただくことを一番の目的にしています。その結果として俳優たちは成長したりもするのですが、それは結果であって、監督は、教育的な効果など気にせずに、才能を見出すために思うことを存分にやっていただければと思っています。
伊藤俊也:わかりました。
マツガエ:いまからさせていただくインタビューは、そのワークショップに参加する俳優たちに、伊藤俊也監督が、どのようなお考えで俳優と接し、どのように映画を作ってきたのかを理解してもらうために行うものです。よろしくお願いします。
伊藤俊也:よろしくお願いします。
マツガエ:まず、伊藤監督と俳優ということで考えますと、僕が思いつきますのは、小柳ルミ子さんのことです。小柳ルミ子さんは、1971年に「わたしの城下町」で歌手デビューをして第13回日本レコード大賞最優秀新人賞を獲得して以来、バリバリのアイドル歌手でした。テレビドラマなどで女優ぽいことは少しはやっていても、多くの人は彼女のことを女優とは思っていなかった。そんな状況のなか、伊藤監督は、1982年、実際の児童誘拐事件を下敷きにした映画「誘拐報道」で、彼女を、まったく泥臭い、アイドルイメージとかけ離れた犯人の妻役で起用します。その結果、小柳ルミ子さんはその年の日本アカデミー賞最優秀助演女優賞を受賞する。さらに翌年、1983年、伊藤監督は映画「白蛇抄」で小柳ルミ子さんを堂々たる映画の主演に大抜擢されます。結果、小柳さんは日本アカデミー賞最優秀主演女優賞を受賞します。小柳ルミ子さんの女優人生を考える時に、伊藤監督に見出してもらったことは、なんて大きいことなんだろうと、勝手ながらに僕は思うんです。
伊藤俊也:まず、私は歌姫としての小柳ルミ子さんしか知らなかったわけですね、演技をされているところは一切見たことがなかった。でも、紅白の時期になりますとね、あの頃毎回出場されていたので、紅白で歌う彼女のね、歌いっぷりというのは知ってたわけです。特に彼女は「わたしの城下町」から「瀬戸の花嫁」とね、立て続けに出てまして、それだけに、私も彼女にはそれなりの関心を持っていたわけです。それで「誘拐報道」の脚本作りをやっていて、いよいよ犯人役を決めようとなり、ショーケン(萩原健一さん)が決まった。次に、色んなキャスティングの中で、特に犯人の家庭を、子供に至るまで書こうと思いましたので、犯人の奥さん役という、これが非常に重要な役だなという風に思ってまして、だからこれはもうほとんど、犯人役のショーケンとの組み合わせで、直観ですね、最初っから小柳ルミ子さんというふうには思ってたんです。
マツガエ:なるほど
伊藤俊也:ところが、ルミちゃんのキャスティングには結構反対する人たちがいたんです。
マツガエ:ええ!?そうなんですか!?
伊藤俊也:そもそも「誘拐報道」という映画は、読売新聞大阪社会部が、実際に起こった宝塚市学童誘拐事件に際しての報道規制を題材にして執筆したルポルタージュを元にしているんですが、そのルポルタージュに出会うより前に、私は日本テレビで、ドキュメンタリー番組の仕事をやっておりましてですね、イタリアのモーロという首相の拉致暗殺事件を、イタリアに相当長期間ロケーションして作ったんです。それが非常に視聴率が高くて評価された。それで次に、全世界にまたがって取材をして、「右手にコーラン左手に石油」というドキュメンタリーを日テレの仕事としてやったんです。その流れで、読売新聞大阪社会部の「誘拐報道」に出会った。私はピンと来ましてね、これは、読売新聞、日テレ、そして私の本拠地であった東映、この三角関係の中でひとつやれば「誘拐報道」を映画にする企画が成立するんじゃないかと。で、実際にその目論見は当たって、映画を作ることになったわけです。そうなると、当然、キャスティングにおいても、日本テレビのプロデューサーたちが関わることになる。そこに、私が、ショーケンの奥さん役として小柳ルミ子さんを提案した。こちらは映画の人間ですから、歌手のルミちゃんが犯人の嫁役をやるというのは意外性のあるキャスティングなわけです。ところが日本テレビ側としてはイヤというほど歌番組でルミちゃんを見ているわけですから、ルミちゃんの起用に意外性がない。それよりは吉永小百合さんや大原麗子さんというような映画女優をキャスティングしてくれと言ってくるわけですが、もちろん吉永さんも大原さんも素晴らしい女優ですよ。でも、こちらとしては意外性がない。
マツガエ:ですよね。
伊藤俊也:結局、歌姫を汚れ役で使うということに意味があるんだということで押し切って、なんとかキャスティングできた、というわけなんです。
マツガエ:なるほど。そういう経緯を聞きますと、やはり、伊藤監督のお力で、小柳ルミ子さんの女優としての道は開けたんだなあと、改めて思います。そして、映画を見ると、あの犯人の嫁の役が小柳ルミ子さんで本当に良かったと思えます。本当に、ショーケンさんの嫁さんにしか見えなかった。いま、うちのワークショップでは、俳優たちに演技の基礎としてマイズナーテクニックというのを教えています。教えていただいているのはボビー中西さんというアクターズ・スタジオの生涯会員の方なのですが、ボビーさんが教える方法は素晴らしくて、目指すのは「役を演じること」ではなくて、そこに「役として存在すること」なんですよね。映画という架空の世界、想像の設定の中で真実に生きること、それこそが俳優の仕事だと教わるのですが、小柳ルミ子さんは、まさにあの映画の世界の中で、犯人の嫁として、過不足なく生きていたし、存在していた。微塵もアイドル歌手だなんて思わせもしません。監督は、どのように小柳ルミ子さんに魔法をかけられたのでしょうか?
伊藤俊也:ルミちゃんは、私が見込んだ通り、ほとんど芸の虫と言っていいような、もう生真面目な子でしてね。クランクインするときには現場に台本を持ってくる必要もないぐらいにセリフもしっかり入っていて、プランを持っているんです。ところが映画はそれだけではだめなのであってね。かたや萩原健一、ショーケンなわけですよ。彼はね、非常に、いわゆる一種の天才といっても良いと思うんですけれども、ルミちゃんとは対照的にセリフちゃんと入っているのかなと心配になるような感じで登場するわけです。芝居もその時々でね、決めてこない。いや、決めているのかもしれないけど、決めているようには見えないし、みせないようにしている。そんな対照的なルミちゃんとショーケンがぶつかって、なにかが生まれるわけです。
マツガエ:なるほど。そういう意味で言うと、魔法というか、ショーケンさんと小柳ルミ子さんという組み合わせによる爆発といいますか、それを仕組んだのが伊藤監督ということですね。
伊藤俊也:組合せの妙味と言うんですか、そういうのは確実にありますね。
マツガエ:それ以外に、伊藤監督が心がけたことって何かありますでしょうか?
伊藤俊也:見ていただいたらお分かりになると思いますが、ショーケン演ずる犯人が子供を誘拐して、いろいろ回った後に、家に戻って、嫁さんであるルミちゃんに会いに来るシーンがあります。犯人は途中で財布を無くしてしまっていて、お金が全然ない。ガソリンを入れる代金もない。どうにかお金を調達しなければいけないと嫁さんのところに帰ってくるんです。すると、そこに自分の娘がいる。娘が「お父ちゃんとならお風呂に入る」と言い出して、娘をお風呂に入れるハメになる。一方、嫁さんの方は、旦那が誘拐なんて大それたことをしているなんて知らないわけです。ただ、日常の中で変な借金取りが来たり、旦那が理由もなく姿をくらましたりで、なんだか悪いことが起こりつつあるんじゃないかと心理的に追い詰められている。そして、その妻の不安のすべての原因が目の前にいる夫なわけです。その夫がふらりと返ってきて、当たり前のように娘を風呂に入れている。そして知り合いから三千万を借りられることになったとうそぶく。耐える女ですからギリギリまで耐えている。すると夫が言うわけです。ちょっと一万円かしてくれないかと。そんなこと言われて、妻がついに切れるんですね。三千万手に入る男がどうして一万も手に入れられないんだと。この一連の緊張したシーンはほぼカット割りもあまりせずに一気に行かないと無理だと思ったんですね。だから俳優たちにはこうして欲しいという芝居のおおよその組み立てだけは伝えて。でも、いきなり撮影するにはショーケンがダメなんですね。セリフがあやふやで。なのでリハーサルを何回かはやるのは仕方がない。でも、リハーサルを三回ほどやったところで(これはそろそろフィルム回さないと逃すぞ)と感じたんですね。というのも、ショーケンはセリフが入っていないときはあやふやなんですが、セリフが入っちゃうと自信を持っちゃって芝居が逆にオーバーになる。それがわかっていたので、セリフが入るか入らないかのギリギリのタイミングを逃すまいと思っていた。それが今回のわたしの大きな仕事だとさえ思っていた。そんなときに、チーフ助監督が「本番テスト!」と言ったんです。が、テストでは困るわけです。ここでフィルムを回さないとまずい。だから、チーフ助監督にはもうそのまま言わせっぱなしで、こちら側の近くには、撮影部も照明部も録音技師もそばに居ましたから、小さい声で、カメラ回しますって伝えて、それで、ヨーイはいカチンとやったんです。そうしたらですね、もう唯一その時だけにしか生まれない、非常にキワドイね、危うい感じの、そしてその危うさがそのまま日常の中の夫婦の危うさに通じるような、そんな非常に良い感じになったんです。で、OKと言ったら、スクリプターが、ショーケンの大阪弁のイントネーションが無茶苦茶よっていうから「いやいやもういいから!もうそんなもんは言うな!」と言ってね。言ったんだけれども、そこでね、役者2人が怪訝な顔をしてるわけですよ。監督がOKってどういうことだと。だって彼らはカメラが回っているなんて知りませんからね。それがテストと言いながら実はフィルム回してたっていうのが分かって、それで当然のごとくショーケンはもう一回やらせてください!って言ってきた。ダメになるのはわかっていましたが、ああ、まあ良いでしょうと。で、やらせてみたら、案の定、ショーケンは熱演を始めて、泣きが入り、オーバーアクションになる。それからルミちゃんの方も、非常に、優等生的な、きちんとした芝居になっちゃってね。几帳面にやってはいるけれども、その前のテイクで撮った、なんかこう、ショーケンの手が伸びてきたときに、胸をフッとこう押さえて、溜息を漏らすような感じが無くなってしまっていてね。だから、取り終えてハイオッケーですとは言ったものの、この熱演の回は使わず、やはり、その直前にゲリラ的に撮ったやつを使ったんです。
マツガエ:いやあ、ほんとうに素晴らしいですね。監督という職業が「見極める」仕事であるのが良くわかるエピソードです。
伊藤俊也:ともかく監督っていうのは、俳優の演技を一番最初に受けとめてやらないといけない。カメラのすぐ脇にいて、俳優の生理、リズム、調子、そういうものを一番先に受け取って、俳優の生理を見抜いて、彼らが一番良い状態でパフォーマンスできるようにしてやるというのが監督の役目なんです。俳優にはそれぞれのスタイルがあるし、盛り上げていき方というのか、そういう周期も別々にあるんです。個人に備わっているある種のリズム感というのか、生理の問題とかいろいろあるんです。だからその違ったリズムを持った俳優たちのリズムを合わせながら撮るというのがね、いかに大事かというのを「誘拐報道」では改めて思いましたね。私にとっては『誘拐報道』の経験というのは非常に大きなものになりました。とくにショーケンなんていう俳優を相手に出来たのは大きな経験ですね。
マツガエ:ほかの作品ではどうでしょうか?たとえば「花いちもんめ」では千秋実さんが第9回日本アカデミー賞最優秀主演男優賞、十朱幸代さんがブルーリボン最優秀主演女優賞を取られています。
伊藤俊也:千秋実さんは非常におもしろい俳優さんでね。千秋さんは以前クモ膜下出血で倒れたことがあって、本人に言わせると「何億万個という脳細胞を失ってるから台詞なんてよく覚えられない」と言うんですがね。そう言われていたのをなんとかこう持ち上げて行ったんですが、チャンスを逃すとね、もうだめなんです。どんどんどんどんダメになっていく。じゃ、どうやってその一回を撮れるのか試行錯誤しましてね。あるシーンでは、私が相手役をしてるんですよ、千秋実さんの。で、十朱幸代さんは私と千秋さんのやりとりをすぐ横で頬杖ついて見てるんです(笑)、それで千秋さんの芝居が出来上がる良い頃合いを見て、十朱さんにバトンタッチするんです。で私はカメラの横に行ってヨーイハイってやる。そこはね、もう十朱さんで助かったんです。もう十朱さんは見ているだけで後はぶっつけ本番でやってもらった。
マツガエ:映画作りと一口にいいますが、映画ごとに俳優たちの異なる組合せがあり、異なる特性がある。それらを瞬時に見抜き、台本やらロケーションやらの沢山の連立方程式を同時に解いて、俳優たちのベスト・パフォーマンスを引き出すように、対策を考える。実に大変というか、面白いというか、映画監督がいかに凄いか、監督のエピソードを聞くとわかります。
伊藤俊也:いかに俳優の特性を知ろうとし、俳優の可能性を見極めようとするかという意志ですね、監督の。それがないと、もうこの程度か、ということにもなりますし。一方、無い物ねだりしてもしょうがないわけでね。俳優にあるものの中で最大限の実力を発揮させるためにはどうしたら良いのか。それには個々の俳優のキャラクターというか、その力、経験も含めてね、見極めるのが仕事です。経験と言ってもね、あればいいわけでもない。むしろ無いならないで、それを良さに変える方法を見つけ出してやらないといけないし、経験があればあるで、それを良さに変える。
マツガエ:伊藤監督が、俳優の特性や整理を見抜くうえで、大事にしていることってありますか?
伊藤俊也:この目でよく見ることですね。最近はモニターがはやり過ぎていますがね。あれはもう本当に邪道だと私は思っています。たしかにね、スタッフを信用できないときには頼りになるんです、モニターは。だって、あれには間違いなく映っているわけですから。ああ、こういう映像になったんだなとわかる。安心できる。でもですね、安心したいというのは、カメラマンを信じていないってことでしょ。信頼できるカメラマンがいれば、見る必要はない。むしろモニターなんて見ずに、俳優をなるべく近くで見て、俳優がいけるのか、まだなのかどうなのかを見抜かないといけない。昔、イメージフォーラムっていう雑誌があるときにね、そのうち監督も俳優もみんながモニターを見て映画を撮る時代が来るんじゃないかと皮肉を書いたんですが、本当にそうなってきているんだなと思っています。やっぱり、それでは俳優の生理、俳優の状態というのを見極めるのは難しいと思うんですよね。
マツガエ:僕は演劇をやっているんですが、演劇というのは俳優と稽古をする時間がだいぶありまして、俳優を見抜くのにも猶予があります。ところが映画というのはほとんどない。そういう中で俳優の本質を見抜くというのはやはり撮影をしながらということになるのでしょうか?
伊藤俊也:幸いなことに映画にも衣装合わせとかなんとかありますから。顔合わせっていうか、あえて本読みみたいなのはやらなくても、そこで大体わかるんですね。ちょっと今のところは調子よくって、いい気になっているとかね。いい気になっていても別に叩く必要は無いわけで、いい気になっているその調子をうまく誘導すればいいわけですからね。そんな感じで、本読みや、読み合わせして、かしこまって深刻な芝居をさせるよりは、よもやま話でもしてもらったほうが、キャラクターがよく分かるなという気がします。ある演出家さんなんか、稽古場みたいなところで事前に俳優たちと会って、内容についてああだこうだ俳優さんに伝えたり、芝居をさせたりする人がいるようですが、私は、そういうのは、ほとんどナンセンスだと思っています。やっぱりその、俳優たちは、それなりの扮装をして、本当の場所に行って、芝居はそこではじめて生まれるものであってね。それから脚本家がね、一字一句変えてくれるなと言ったりするでしょ。そう言いたくなる気持ちは良くわかるんですよ。でも、そんなことよりも、現場主義に立てばね、それはもうそこに書かれている一行よりははるかに良い一行が俳優たちから生まれる可能性があると思うんですよ。だから、監督は、脚本家の言葉を越えたセリフを俳優が生み出す瞬間を受け止めてやる力がないといけないんです。そのためにも、監督は、作家や脚本家よりも詩人でないといけない。時と場所によるインスピレーションを受けて、想定と違う事態を受け入れることができないといけない。
マツガエ:現場で生まれる物を信じるということですね。
伊藤俊也:「誘拐報道」で、ショーケンが誘拐した少年を連れていて先を急いでいるところ、寒さに耐えかねて少年が「おしっこしたい」と言い出して、ショーケンがめんどくさがりながらも、積もった雪におしっこをさせる場面があるでしょ。あれは、シノプシスの段階から私の中にはイメージがきっちりあったんです。小便が湯気を上げ雪に黄色いシミが出来て雪に穴ぼこが開くというようなことを考えていたんです。だから、ショーケンが少年を抱えて小便をさせる引きの画を取ったら、次には近づいて小便が雪に穴をあけるアップを撮ろうと思っていたんです。あの撮影は、少年は本当におしっこを我慢していて、本物をさせているんですけどね、撮影の段取りなんてしている間に我慢し過ぎて少年のおしっこが出なくなっちゃってね。出ない出ないとなって、そうしたらいつの間にかショーケンが、シーっなんてやって、おしっこを促したんですよね。そうしたらおしっこが出てきて、そのまま全部出させてやったんです。そしておちんちんを仕舞ってあげてね、そうすると、ショーケンが少年の体をさすり出したわけです。寒い中で小便をしていたわけですから少年の体が冷たくなっていて震えている。だから脚本にそんな指定はないし、打ち合わせにもないけど、ショーケンはおもわず寒さに震える少年を思わずさすったんですね。それがショーケンの才能なんです。このおしっこのシーンは、お金のために少年を誘拐した男が少年にほだされて人間味を持ってしまう犯人としては躓きの石になるシーンであって、そう考えると、雪に穴をあけるおしっこのアップよりも、少年を温めようとさする犯人の画の方がどれほど大事かということなんです。だから、私はそのままカットをかけずに回してみていると、そのうち、ショーケンがキョロキョロし出した。つまり忘れて犯人は少年におしっこをさせたり温めたりに夢中になってしまったけど、誰かに見られてやしないか不安になったんです。そして、キョロキョロした。私はそこでカットしたわけですけど、そんなことを俳優にやられた日には、もう雪に穴ぼこなんて紙の上で考えたシーンはいらないわけです。だから、それは撮りませんでした。
マツガエ:現場で生まれることを撮る。含蓄深く、また、なんとも素晴らしいお話です。
伊藤俊也:そういう俳優と監督との、丁々発止のなかでの、ある瞬間、息の通じるみたいな感じの瞬間ですね、そういう時というのが俳優にとってもそうだろうし監督にとっても、ある種、至福の時なんですよね。そして、そういう時がやっぱり一番良いショットが撮れる時だという気がしますね。
マツガエ:監督の、その俳優や人間を見抜く力というのはいつ培われたんでしょうか?
伊藤俊也:私に特別に眼力があるとは思いませんが、でもそうですね、経験ですかね、それから、わりと私は、子役との出会い、あれが役立っているのかもしれませんね。
マツガエ:子役の出会いというのは?
伊藤俊也:いまお話しした「誘拐報道」の誘拐される少年を演じた和田くんや、ショーケンやルミちゃんの娘役をやった高橋かおりちゃんとかもそうですし、一番最初は、「犬神の悪霊(たたり)」でキャスティングした長谷川真砂美ちゃんでしたね。オーディションで選んだんですが、結構な数の子役に会ったんです。でも最初に会った時にこの子だとピンときた。ところが五人の審査員で投票したらね、私しか彼女に入れていないんです。どうやって彼女を良いと他の審査員に言ってもらうかと思ってね。その時の撮影の仲沢半次郎さんに見てもらったら彼だけは僕と同じ意見だった。それで意を強くしたんですが、他の審査員に認めさせるためには明らかに彼女が良いことを皆に見せないといけない。それで台本に関係ないことなんかをやってもらったりして、私がいろいろ仕掛けたんですね。そうしたらフアッと彼女が実力を発揮してね、最終的には認めさせることができた。それから、一度だけ舞台の演出をやってるんですが、1979年に市原悦子さんのサリヴァン先生で「奇跡の人」の演出を芸術座でやっているのですが、ヘレン・ケラー役の少女をこれも児童劇団でオーディションをして。でもヘレン・ケラーは天才少女なわけですよ。会う子会う子達者な子はいるんです。いるんですが天才じゃないんです。天才を見つけないとダメなんだと私は言っていたんですがどうしてもいない。困ったときに、児童劇団の人が、受験勉強中で出せなかったんだけど一人それらしい子がいると言って連れて来たのが14歳の荻野目慶子だったんです。
マツガエ:荻野目慶子さんは確かその舞台が彼女の芸能界デビューでしたよね、まさに天才女優を伊藤俊也監督が発見したわけですね。なんともすごい眼力ですね。しかし、そのような子役との出会いが、どうして伊藤監督の俳優を見抜く力を磨いたんでしょうか?
伊藤俊也:まず大人と子供の違いというのを考えると、子供は正直なわけですね。出来ないことはできないし、無理にやっても、無理が顔に出てしまう。顔に出るということは、フィルムに映ってしまうわけですから、良くない。だから子役に最大限、力を発揮させようと考えると、自然と、彼らがそれをしたいように仕向けるしかないし、それをするように仕向けないといけないわけです。こっちが、こうしてくれと言えばやってくれる大人ではないので。だから子役が作品の鍵を握るような作品を重ねるなかで、子役と付き合うことによって、結果として、俳優、つまり子役の立場になって考えるようになり、子役、すなわち俳優がよりよくパフォーマンスできるようにといつも考えるような回路が私の中にできたということは言えるんだろうと思うんです。
マツガエ:「ロストクライム」も面白く見させていただきました。なかでも、興味深かったのは、メイキングに映っていたんですが、伊藤監督が、主演の渡辺大くんに演出をしているところです。監督が大くんを呼び出して「きみの芝居はソツがない。ソツがないということは安定しているということで、安定しているということは安心して任せられるということだから悪くはない。だけど、主演をやる者は自然にやることだけではなくて、突出しないといけない。下手をすると芝居臭くなるようなところまで突出して、しかもそれを一段上のところで自然に見せないといけない」というようなことを伝えていました。いま世界的に芝居臭くないナチュラルな芝居が求められるところ、ソツがないレベルの自然と、一段上の大きくドラマチックな、けれども大げさではない突出した自然があり、俳優というものは、手前のソツガない自然ではなくて、一段上の突出した自然を目指していかなければいけないということを強く感じました。「誘拐報道」のショーケンさんの芝居なんてまさに「突出した自然」だと思いますし。
伊藤俊也:俳優によっていろいろあるんだと思いますね。なんか目立ってこういうのをやってやろうとかね。そう思っている野心的なタイプに対しては、むしろその野心を叩いてね、余計な事をするなって言う感じで押さえるのもありかもしれない。でも、その余計な事をする奴の良さっていうのもそれなりにあるわけですからね。一回はたたくけれども決してそれで抹殺しようということではなくってね。ある時に、その余計なことをすることが役立つ日も来るかもしれない。逆に(渡辺)大ちゃんみたいな非常に素直な人には極端な刺激を与える必要もある。もっとやれと言う。だから人を見極めて、ある種の振幅を与えてね。その人の良さを引き出したうえで、もうひとつ上の所を目指すと言うようなことを示唆するのが私の役目かなと思っています。
マツガエ:ありがとうございます。あと、ワークショップに来る俳優にどういう事を期待されますか。どういう人と会いたいみたいなことはありますでしょうか?
伊藤俊也:今度の作品でいえばね、若い感覚、二十歳前後というかね、まずそういう人たちの登場するシーンも多いですし。また、年輩者もね、結構、大臣クラスとか。色々ありますのでね、ま、それはそれで誰に来てもらっちゃ困るということはないです。どなたでもね、大歓迎です。可能性はあります。これは私の信念なんですが、誰にだって才能はあるわけだし、特に俳優をやってみようかという人にはね、カメラ向けられると恥ずかしがる人たちよりは可能性っていうものがあると思っていますから、自分で自分の可能性をつぶさずに、大胆にやってみるということは大事だと思いますね。いつも言うんですが、俳優という仕事は、1に想像力、2に想像力、3も4も5も全部想像力なんだと思うんですね。イマジネーションをどれだけひろげられるかが勝負なんです。例えば、台本には一行「ウェイトレスがコーヒーを2つ持ってきてテーブルに置き立ち去る」ということしか書かれていなくてもね、そのウェイトレスがどういう女の子なのかなと想像力を働かせることが大事でね。店長に嫌がらせを受けているとか、家でろくでもない彼氏が待っているとか、仕事だから嫌々接客してるのか、逆に好きでやっているのか。そんなことをいろいろ考えて演じる。するとその一行の表現には無数のやり方があるわけであってね。これやったら怒られるなとかあると思うんですよ。怒られるのは怖いからやめておこうとか。でも時にはね、それをやってみたらいいんです。きっとおそらくね、一番最初、余計な事をするな、って監督には言われるでしょうね。でも言われても良いじゃないかと。言われたら素直に元に戻せばいいわけで。だけど、ちょっとそういうね、いたずらをするわけではないけども、そういうことをどんどんやってもらいたい。で、やればやるほどね、おまえ余計な事するなと、いつも、何かやろうとして、カメラに映ろうとして邪魔だ、と言われるかもしれない。けれども、以外と面白いやつだとみられることも、ある…かもしれない。わからないですがね。良い例だとは言わないけれども、小林稔侍という役者がいてね、あれはちょうど東映に私と同じくらいに入ったんじゃないのかな、私の助監督時代からずっと出ていて、彼も下積みで居たわけです。わりと役もついたりしているんですけど、ほんと最初のうちは何かというとね、出張ってきてね、お前邪魔だ!てよく言われていたわけですよ(笑)。それが必ずしも、他の俳優にも当てはまるわけではないですが、お前邪魔だ邪魔だといわれながらも、まあ欲があるとみられるのか、あるいは面白いやつとみられるのか、それは監督との関係ですからね、わからないけれども。稀に、面白いじゃないかと、いい役で使ってくれる監督に出会ったりする。どうなるか分からないけど、少なくとも想像力を巡らせる。それを行動にしなくったってね、自分の中でね、感じ方とか違ってくるし、そうすると表情だって変わってくる。表情だけだって芝居はできる。テーブルに珈琲を置くのだけだって色々な表現がある。そういうことはともかくやれるんだからやってみればいい。折角そういうシーンを与えられたときには、そういうことで楽しみなさい、面白がりなさいと思うんですよね。
マツガエ:示唆に富むお話をありがとうございました。ワークショップが楽しみで仕方ありません。今日は貴重なお時間をありがとうございました。
(2018年11月13日、赤坂にて)