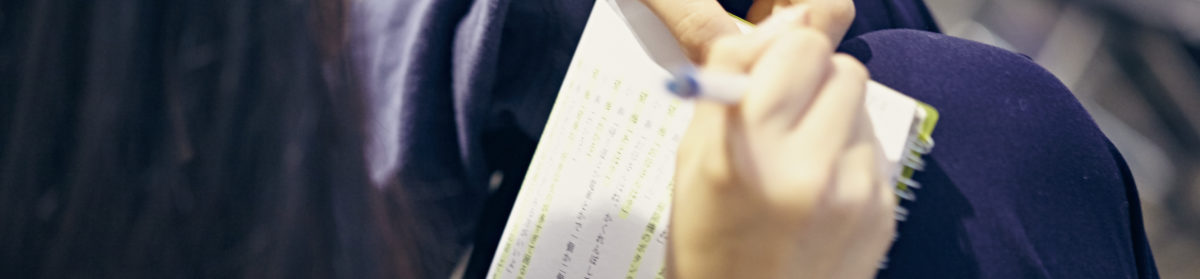2018年12月13日から16日までの4日間、「内田伸輝監督による俳優のための実践的ワークショップ」が行われました。開催にあたり、講師である内田伸輝監督に緊急インタビューをしてきました。今回は、ワークショップを機に映画を作る予定なので、どのような映画を作りたいかと言うようなことを含め、色々お話をしてきました。聞き手は、アクターズ・ヴィジョン代表・松枝佳紀(まつがえ・よしのり)です。
「なぜ映画を作るワークショップにしたのか」
マツガエ:内田伸輝監督作品は、出ている俳優たちが演技しているようには見えない。本物を単に映しているようにしかみえない。実際の事件に出くわしているんじゃないかと、そう見る者を錯覚させてしまうような凄さがあります。だから、内田伸輝監督にワークショップをやってもらえるなら、映画を撮ってもらい、俳優たちを本物に変貌させてもらうしかないと思って、そういうことができるのは内田監督以外にあまりいないと思って、今回「必ず」映画を撮るワークショップにしたらどうかなと思ってワークショップの講師を依頼しました。
内田伸輝:アクターズ・ヴィジョンでは、これまで映画を作ったりしているんですか?
マツガエ:今年のフィルメックスで招待作品として一日だけ上映される斎藤久志監督の新作「空の瞳とカタツムリ」がアクターズ・ヴィジョン製作映画の第一弾です。本格的に公開になるのは来年の2月ぐらいなんですが。
内田伸輝:それは斎藤監督のワークショップが元で作られたものなのですか?
マツガエ:それが、この映画はもともと、2016年にやった荒井晴彦監督のワークショップが出発点なんです。ワークショップで荒井晴彦さんに聞いたアイディアが面白くて、それをどうしても映画にしたいなとお話をしたんです。で、そのワークショップに縄田かのんという女優が参加していて、荒井さんが気に入ってくれて、じゃあ、縄田かのん主演でその映画をやろうということになって、原案を荒井晴彦さんとして脚本は荒井晴彦さんの娘さんの荒井美早さんが書くことになって、監督は荒井さんが信頼している斎藤久志さんでとなって、ほかにアクターズ・ヴィジョン内でオーディションをして、もう一人主演に中神円、それから藤原隆介くんに出てもらうという流れで作られたんです。
内田伸輝:初めての映画作りは大変だったんじゃないですか?
マツガエ:想像を絶するほど大変で(笑)とくに金銭面、いまもそれは続いているのですが。とは言うものの、第二弾をすでに作っていて、まあ、こちらは、お金は僕じゃないので、そういう面では大変ではないのですが、先日撮り終わり、これから編集です。天野千尋監督で、篠原ゆき子さんにも出演してもらってます。
内田伸輝:そうなんですよね、篠原ゆき子さん主演で撮られているんですよね。僕も「おだやかな日常」で篠原さんが主演されていて、いつかまた篠原さん主演で撮りたいなと思っていたから、先にやられてしまってくやしくて(笑)篠原さんも松枝さんのワークショップ参加者なのですか?
マツガエ:彼女は、天野千尋監督のワークショップには参加していなくて、物語の内容から考えてのオファーです。もう一人の主演は大高洋子さんという女優さんにお願いしているのですが、彼女は天野監督ワークショップ参加者で、とても魅力的な女優なのですが、僕が作ろうとしなければ彼女主演の映画はもしかしたらこの世に無かったかもしれない。という感じで、僕がいたからこそ、その映画がある、その人が大きな役で能力を最大限発揮できた、と言うようなキッカケに僕は非常になりたくて、内田さんとも、そういう映画が作りたい。僕と内田さんが組まなかったら出来なかった映画、このワークショップがなければ、世に出ることがなかったかもしれないような俳優たちをメインに据えて作られた映画をつくりたいです。
内田伸輝:僕も同じ気持ちですので、映画を撮らないかという話をいただいて本当にうれしかったです。
「塚本晋也監督と是枝裕和監督」
マツガエ:今回、内田伸輝監督作品の特集上映がちょうどありますし、参加俳優たちも、監督のほぼほぼ全作品を劇場で見てもらえるという素敵なタイミングでもあって。まずは皆には、内田伸輝監督作品を見てもらいたいんだけど、簡単に、内田伸輝監督作品の、僕の印象を言わせていただくと、なんというか、凄まじいんですよね。人間の恐ろしい部分を圧倒的なリアリティをもって丁寧に描いているという印象です。塚本晋也監督作品に近い。とくに僕は塚本晋也監督の「KOTOKO」とか大好きなんですけど、塚本さんの描くものと通底するものを内田伸輝監督作品には感じます。
内田伸輝:実は、塚本晋也監督に僕は16,17歳の子供のころからあこがれていまして、どうやれば塚本監督のような自主映画が作れるのかっていうことをすごく勉強してたんです。
マツガエ:ああ、そうなんですね。腑に落ちました。
内田伸輝:そのほかに影響を受けたということで言いますと、塚本晋也監督と、それから是枝裕和監督ですね。御二方のことは大尊敬していますし、ドキュメンタリー映画ですと、原一男監督や想田和弘監督の映画で人間描写を勉強しています。
マツガエ:内田さんの作品は全てにおいてドキュメンタリーな作りをしていますから、是枝監督の影響があるのは納得です。でもそういうことで言うと、是枝さんは「家族」とか「子供」がテーマとしてある訳じゃないですか。精神の危うさは全然描いてないと思うんですよ。でも内田さんは、人間の精神の危うさみたいなものを、ほぼ描いている。そこは塚本さんの影響なんですよね。ということで言うと、内田さんは是枝さんと塚本さんのちょうど間に居るという感じですね。
「フィクションを取材する」
内田伸輝:是枝さんは、そのキャリアをドキュメンタリーから始めて、のちに映画というフィクションを作るようになったのですが、是枝さんが「誰も知らない」のメイキングで仰ってたことがあって、その影響をいまでもぼくは受けているんです。それは是枝さんにとってドキュメンタリーの制作も、フィクションである映画の制作も同じだということです。つまりドキュメンタリーは「事実を取材して作る」んだけど、映画は「フィクションを取材して作ってる」と仰っていて。なるほどと思いまして、僕も「フィクションを取材する」という考え方で映画を作るようにしています。
マツガエ:いまやドキュメンタリーなタッチで語られる映画は世界映画の潮流です。フィクションにおいても、例えば、クリストファー・ノーラン監督以降のバットマンなんて、恐ろしいほど細部までドキュメンタリーな感じで作られている。フィクションやファンタジーであっても、そこにドキュメンタリーな構造が備わっているというのは世界では当たり前になっている。なぜなら、ドキュメンタリーな構造を持っているということは、それだけ物語や人物に信憑性を与えることになり、観客に強くメッセージを伝えることができるようになるからなんですね。そして、そのようなドキュメンタリーな構造を持つ映画を作ることにおいての大事なことは、架空の物語や架空の登場人物が、実際の事件や実際の人物であるかのように、ノンフィクションのこととして、いかなる取材をも受けることのできる強靭なレベルで作り込みがされているということだと、僕は考えています。
内田伸輝:ほんとうに、まさにそうですね。
マツガエ:いま、アクターズ・ヴィジョンでは、俳優たちに、アクターズ・スタジオ2番目の日本人会員でもあるボビー中西さんにマイズナー・テクニックを伝授してもらっているのですが、中級・上級レベルでは、俳優が役のキャラクターにドキュメンタリーな構造を持たせるための訓練をやるんです。俳優たちにキャラクターを作らせたあと、ボビーさんが、もしその人物が実在の人物であるならば俳優が知っておらなければならないようなことを、徹底的に質問するのです。ボビーさんは冗談で重箱の隅をつつくような質問と自ら言うのですが、そういう細かな質問を沢山します。この質問攻めが、取材にあたるものなのですが、それにちゃんと応えられるようでなければ、キャラクターの作りとしては駄目なんですよね、曖昧に答えたり、その場の思い付きでそれっぽく答えても、それが嘘であるのは伝わります。真実であると伝わるには、その細部を事実として持ってないといけないんです。つまり、たとえ架空の人物であってもドキュメンタリーな構造を持っていないといけないということです。そのようなキャラクターづくりを当然のようにできる俳優となるべく、いまボビー中西さんに鍛えてもらっているんです。
内田伸輝:それは本当に有意義なことだと思います。まさに「フィクションを取材する」ということを実現するには、俳優側が取材を受けるに値するドキュメンタリーな存在でないといけないですもんね。そういう意味では、僕も、自分の映画の現場でも、そこを作ることに最も時間を割いているかもしれません。
マツガエ:そうなんじゃないかと想像していました。内田伸輝監督の映画に出てくる人物はみんなガチに見えます。それは俳優たちがドキュメンタリーな構造を内面に持つまで追い詰めているんだと想像します。だからこそ内田伸輝監督の作品は海外で評価される。僕的には、そうやって俳優たちをガチの領域まで追い込む内田伸輝監督の真実の現場で鍛えていただきたい。その思いがこのワークショップをやろうと思った全てなんです。
「真に迫る演技は「目」が違う」
内田伸輝:表面的な演技っていうのは、練習をすれば、割とみなさん誰でも出来るようになります。喋り方だとか、イントネーションだとか、そういったのは修正すれば、出来るようになるんです。だけど、結局、表面的な芝居は、真に迫って観えない。結局、それっぽくみせてるだけの演技だとバレてしまうのです。
マツガエ:真に迫る芝居ってどこが違うんでしょうか?
内田伸輝:目です。僕は演じる上で、特に「目」にこだわるんですね。顔が無表情でも、目が違ってくるだけで、伝わって来るものの迫力が変わる。目が違うというのは演じていない証拠で、一番大事なところです。
マツガエ:たしかに「目」が変わるっていうのは、ガチでその人になるってことですからね。表現というものを超えている。たとえば親を殺した人の「目」になるっていうのは、本当に親を殺さないとこんな「目」にならないだろうという「目」になるってことですから、もはや親を殺しているのと同じ状況に俳優はなっている。しかし、そういう「目」に俳優をさせるために、内田伸輝監督はどのような方法を取られているんでしょうか?
内田伸輝:僕の方法はただひたすら何度も繰り返すという方法をとっています。僕は演出で怒鳴ったりはしないんですけど、その「目」になっていない、って事を優しく指摘して、妥協せずに何度も何度もやり直すんです。
マツガエ:あああ、それは苦しいでしょうねえ。
内田伸輝:本当にムカついてる人とか、いますからね、やっぱり。でも、ムカつかれても怖くないんですよ。
マツガエ:ダメなものはダメなんですね。
内田伸輝:そうですね。すごい僕のことを睨んでくる人とかいるんです。
マツガエ:いるんだ!? 俳優で!?
内田伸輝:はい、何度もやり直してると。でも、その睨みですら、これは本当の睨みじゃないなって。わざと睨んでやろうみたいな意識で睨んでるでしょ、みたいに見えてくる。だから、ダメなものはもう一回やり直すというだけの話なんです
「演じなくなるまで、演じさせる」
マツガエ:本当にそういう意味では内田さんの映画は、みんなガチの人にしか見えないので、すごいなって思うんです。本当に頭おかしい人にしか見えない。監督がちゃんと俳優をそこまで連れて行ってくれている。だから「ぼくらの亡命」の鼎談の時にもお話しましたけど、海辺のラストシーンが、ああなるのは、監督も思ってないし、俳優ご本人も思ってない訳じゃないですか。監督も俳優も何が起こるだろうと探り合う中で、ぽつっとある真実が生まれる。それがその場で生まれるまで何度もやって、思考がなくなった時点でそれが本当に生まれる。その瞬間を撮ってるんですよね。
内田伸輝:ほんとうは、感情的になればなるほど人間て考えないじゃないですか。反射で動く。なのに演技になると、俳優は、感情的になるシーンでも、考えて、練って練って演じようとしてしまう。すると、その俳優の芝居は、どんなに洗練されていたとしても、結局、考えて、練って練ったものがそのまま出てきているんですよね。どんなにやっても反射でやっているようには見えない。だけど、それを思考がなくなるまで繰り返すことによって、本物の感情が動き出したものが撮れてくる。僕の現場ではそうやって、俳優から本物を取り出します。俳優の思考が見えるような演技では、僕自身も満足いかないし、世界では通用しないですから。
マツガエ:それなんです。内田さんに、うちのワークショップに来る俳優たちを導いてほしいのは。世界で戦えるレベルに連れて行ってほしいんです。彼らの自慢できる代表作、いや、もはや遺作にしてもいいような、演じた彼ら自体がこれが俺のすべてだと言えるような決定的な一本を作ってほしいんです。そんな一本を内田さんになら撮ってもらえる気がするんです。
内田伸輝:はい。僕も心中してやるぐらいのやつ、撮りたいですね。どの作品を作る時も僕は常にガチなので大丈夫です。
マツガエ:俗に、ガチの状態になるために俳優を限界的な状況に置く演出方法を「追い込む」とか言うじゃないですか。世間でよく言われるそれは、もっぱら、怒ったり怒鳴ったりの恐怖で俳優を追い詰める方法なんですが、内田伸輝監督の方法もそうなんでしょうか?
内田伸輝:追い込まれたいって思っている俳優って結構いますからね。違う自分を見てみたいっていうのは。ただ、怒って追い込まれると、本物が出ると言うよりは、結構割とその時の萎縮した感情が出てきてしまうという気がします。その委縮した感情がそのシーンだったり役として必要なものなら良いのですが、そうじゃないときに怒っても、違う部分しか出てこない気がします。それに怒られて追い込まれてガチになることを俳優が覚えてしまうと、その俳優は演出家にそうされないとガチになることができなくなる。それだと、もう特殊な演出の元でしか使い物にならない俳優になってしまう気がします。だったら、これがこうだからダメなんだよと冷静に追い詰められる中で、何度もやり直していくうちに、何かふとした瞬間にそれが出て来るという、方法の方が良いんじゃないかと思っています。実際、そうやって一端どこかクリアすると、みんな割とそこからトントン拍子で進んだりするんです。だから実体験として思うのは、怒られてガチになるよりも、そうやって冷静に追い詰められていく方が、俳優にとっても、その感覚が身になっていくんじゃないのかなと思いますね。
「どういう映画を作るか」
マツガエ:ワークショップをやることは決めました。あとはどういう映画を作るかですよね。
内田伸輝:どういう映画を作りましょうか。
マツガエ:今回のワークショップの話は、内田伸輝監督のクリエイターとしての感性を頼んでのことですので、当然、内田さんが作りたい物を撮ってくださいということなのですが、あえて僕からお願いするとすると、社会性のある話にしてほしいということがあります。
内田伸輝:ああ
マツガエ:というか僕に言われないでも、内田伸輝監督の映画はすべて社会派ですからね、何の心配もなかったですね(笑)
内田伸輝:どうこねくりまわしても、社会性に関しては必ず持った映画になっていると思います。実際、何らかの日本の現状や、世界の流れ、みたいなものが映画の中で見えてこないと、僕の中で面白いと思えないので。
マツガエ:目の前にある世界や社会に対してのひとつの行動として映画があると僕は思ってます。たとえ作った映画が偶然普遍性を獲得して、何百年後にも観られることはあるとしても、そんなのはたまたまもらったご褒美に過ぎなくて、やっぱりいま目の前にある憎むべき世界やら悲しむべき事態に対しての怒りや悲しみや、あるいは提案、あるいは、褒めたたえるべき出来事への惜しみない賞賛、そういうものが映画なのかなと思うので、いまという時代性、ここという社会性は抜いては映画はないと思うんです。そう思って作られた映画は必ず世界を変えていく。僕はそう思っているし、きっと内田伸輝監督もそう思っておられるように思うんですよね。
内田伸輝:同じです。そう思っています。例えば恋愛映画も、そこに普遍性と、今の時代を映す社会性があるのなら名作になると思っています。なので、僕は常に、普遍的な人間の葛藤と、今の時代を映す社会的な葛藤を描いた映画を作ろうと心がけているんです。
マツガエ:その内田さんがいま映画にしたい題材とかありますか?
内田伸輝:先日、3年4か月もシリアの武装勢力に拘束されていたジャーナリストの安田純平さんが解放されたじゃないですか、そしてそのあとに、日本では「自己責任論」が巻き上がりました。安田さんは誰に命令されたわけでもなく、日本政府が危険で立ち入るなと言われている戦地に自ら足を踏み込んだのであって、その責任は安田さん自身にあるのであって…というような議論です。そのニュースを見ていて、どうやっても日本人は「自己責任」というものを問うのが好きなんだなというふうに僕は思ったんですね。安田さんの事例に限らず、たとえば、誰かが圧倒的なミスをした時に、それを皆で寄ってたかって叩く、祭り上げて晒して叩く、そういう傾向があるんだなって僕はもともと感じていて、そういうことをぼんやりと、なにか作品にしてみようかな、と思ったりしています。
マツガエ:やばい。もうそこでかなり面白そうです。あとは日本に問題を提起できるような作品になるといいですね。いや、内田伸輝監督の作品なら、もうそうなるのは目に見えていますが。
内田伸輝:作るからにはそうなってほしいですね。そう考えると、まだまだ調べないといけないこと、考えなきゃいけないことがあります。
マツガエ:ワークショップで俳優たちを見ていて気付くことや思いつくこともあるかもしれませんしね。
内田伸輝:本当にそう言うことはありますね。一緒に考えて一緒に何かを発見できて、一緒に世界に問いかけることのできる俳優さんたちと、ぜひ出会えることを楽しみにしています。
(2018年11月6日、新宿三丁目にて)